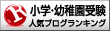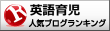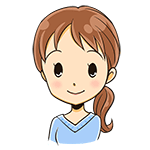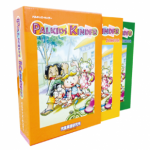生成AIの利用が当たり前になり、noteやSNS(X・Threads など)にも、AIが書いた文章があふれるようになりました。
ChatGPT特有の「クセ」があるため、使い慣れた人が読むと一瞬で「あ、これはAIだな」と分かってしまいます。
SNSでは、有名人やビジネス系アカウントがAI生成の投稿を堂々とアップし、そこに大量の共感コメントが並ぶ光景も珍しくありません。
そんな場面に出会うと、「なんだかなぁ・・・」という気分になります。
私も毎日のようにそんな投稿にでくわします。心の中で「ださいなっ」って思ってますw
いまの中学生以下の世代は、スマホネイティブを飛えて「AIネイティブ」へと進んでいくでしょう。
学校の課題・レポート・英語ライティングなどでも、AI利用はすでに広がっています。
子供もクラスメイトでも、こっそりAIを使用している子たちもいます。
明らかに英語力が低く、ライティングが下手な子が、AIをこっそり使って、高度な語彙を使いこなしたレポートを書いていたり・・・
いくらAI検知ツールがあるといっても、完璧にチェックできるわけではないので、先生方も判定が難しいのでしょうね。
ただ、本人の実力以上のアウトプットだと、正直バレていると思います。
塾や学校がいくら「AIを使うな」といっても、思考が未熟な子ほど、は楽だしいいのができるから、使ってしまうんですよね。
もちろん、うまく使いこなせる子は思考の整理が進み、より質の高いアウトプットができるようになります。
一方で、基礎力がないまま文章を丸ごとAIに任せてしまうと、自分の実力が伸びないまま止まってしまうリスクもあります。
かといって、周りがどんどんAIを使う時代に「危ないから」「実力がつかないから」と完全に遠ざけてしまえば、パソコンを使いこなせない「PC音痴」ならぬ 「AI音痴」 のまま大人になってしまうリスクがあります。
だからこそ、親としては、子どもとAIとの距離感を見守りながら、どのように関わらせるかを考えていく必要があります。