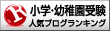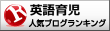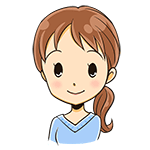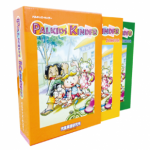思考力、アクティブラーニング、探究学習といっても、基礎土台がない子がしても無理がありますよね。議論の深掘りができません。
一冊も読めない子が読解力高いわけがない
読書も同じ。
読解力といっても、月1-2冊しか読まない子と毎日何冊も読んできた子では、圧倒的な差がついているのは明らか。
読めない、書けない子が読解力が高いなんて話、聞いたことがありません。
昭和の沢山遊んだ子どもは、思考力の高い大人になっているのか?
昭和の子ども時代、学校が終わると玄関にランドセルを置いて外に遊びに出た子どもたちが多かったですよね。
ファミコンや外遊びばっかり。いい時代でしたね。もっと上の世代はメンコや缶蹴りとかでしょうか。
しかし、そんな遊びを経てきた今の大人たちが、思考力の高い、創造性がありクリティカルシンキングができる大人になってますかね?大半は平凡サラリーマンじゃないですか?
むしろ、日本ダメになってませんかね。使えないオジサン、頭の固い男尊女卑じいさんによって。
子どもは遊びが大事!低学年は遊ばせないと!と受験否定派はよく言いますが、本当に遊びが役に立っているんでしょうか?
(低学年から勉強優先がよい、と言っているわけではありません)
少数の経験談で語るな
教育の話になると、少数の経験談を例に語る人が多すぎます。
n=1の例を見るのではなく、統計的に結果を見ないと。
反復学習も未来型アクティブラーニングもどちらも必要。ただし、過度の反復学習(地理名記憶など、ただの暗記物)や過度の受験算数は不要。そう思います。